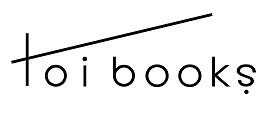『ぬしはひとの道をゆくな』 チャン・ソク
チャン・ソク詩選集
『ぬしはひとの道をゆくな』
チャン・ソク 著 / 戸田郁子 訳
CUON / 四六変形判並製 / 216P
大海原で
知を詠い、人を詠う
チャン・ソクは、かつて森の若いクヌギだった炭の声で宇宙を語り、
錆びた釘とひずんだ板のかたい抱擁に自らの死を哲学し、
生の全貌にふりつもる初雪の下に〈愛〉を探す。
彼の詩を読むと、自分の詩がいつしか忘れていたものが
見えてくる。まだ間に合うだろうか。
もう一度最初から書き始めよう。
――四元康祐
目次
一部 風が吹いてくる 散らばれ
二部 すべての宇宙がわたしの背後だ
三部 おいしいひとになります
四部 つぶれて踏みにじられた血の跡
五部 波はおのれの道をゆくもの
解説 紅梅の銀河にひびく人間の歌(四元康祐)
訳者あとがき
作品一覧(原著掲載順)
前書きなど
●「訳者あとがき」より
詩人としてのデビューは早かった。ソウル大学国語国文科に在学中だった一九八〇年元旦の朝鮮日報朝刊に、「風景の夢」が、新春文芸詩部門の当選作として発表された。しかしその後四十年間、チャンさんは作品を発表しなかった。書けなかったのではなく、強い意志を持って詩から遠ざかったのだ。
文学を志して通った大学だが、仲間たちは民主化を叫んで次々と投獄されていった。当時は「参与詩」と呼ばれる民主化運動の詩が主流だったが、詩を書く立場になってみると「外に出よ、闘え」のような詩は、どうしても書けなかった。むしろ額に小さなあかりを灯す深海魚のように、存在の根源を探るような詩を書きたいと熱望した。それが「風景の夢」だった。
「文学を行うことは長い間の夢でもあったが、世の中の動きは理想とは乖離していた。私の詩的な悩みは時代とは嚙み合わず、緊迫した時局の中で夏空をじっと眺めているような情緒は、仲間たちにも受け入れられなかった」
一九八〇年四月、兵役に就いて外界の喧騒から遮断され、光州での蜂起も知らずに過ごした。三年たって除隊した後は、理想と現実のギャップに苦しんだ。
「もう詩は書かない。そうすれば少なくとも、偽善的な詩は書かずにいられるだろう」
詩への未練も大学生活も、すべてを捨てて、父が経営する牡蠣の養殖場のある南の海に向かい、二十代後半から三十代をひたすら海と向き合って過ごした。その間、独裁政権は覆され社会は変革した。
ある日、仕事場に高校時代の親友魯會燦氏が突然訪ねてきた。魯氏は大学時代に学生運動から労働運動に身を投じて拘束された後、政治家の道を歩んでいた。「なぜ詩を書かないのか」と友は問い、「詩を書くのがいい」と励ました。
(中略)
大学でチャンさんは文学に没頭し、魯氏は学生運動に身を投じたが、離れていても心はいつも通じ合う友だった。その友と壮年になって再会したことが、チャンさんの心を再び社会へ、詩へと向かせるきっかけを作った。しかし二〇一八年に突然友を失い、彼を偲ぶ詩を書かずにはいられなかった。本書の「日時計」「背後」「宇宙論」のほかにも、亡き友を詠った詩がいくつもある。
二十代初めに書いた「風景の夢」を、長く記憶にとどめていた人々がいた。後になってその詩が、韓国詩壇に一つの潮流を作ったという評論も書かれたが、詩を書いた本人は長くそれを知らずに過ごした。
四十年余りの時を経て書いた「煤けた告白」には、「風景の夢」に登場した“つめたく燃える鳥”のイメージが再び出てくるが、それは決して意図したものではなかった。混沌とした現実を冷徹に見据え、そこから飛び立とうとする鳥のイメージが、詩人の胸の内にずっと棲み続けていたのだ。
「現実を知らずに過ごしたという痛みが、それからもずっと私を苦しめ続けた」
チャンさんはかつての民主化闘争などの記録を読み漁り、そこに自身が参与しなかった痛みに呻吟した。その痛みは、現実を深く見据えようという姿勢となって帰着した。
三百人余りもの犠牲者を出したセウォル号の事故や、韓国全土を揺るがせたロウソクデモによる大統領への弾劾、それに世界的なパンデミックなど大きな事件に直面するたび、自分が発言しようという自覚を持ち、熾烈に創作したいという欲望に駆られるという。
突然訪れる「詩的瞬間」を一つも逃したくないという思いから、チャンさんは胸のポケットにいつも小さなノートとペンを持ち歩いている。
「詩がこの世界に作用する力は何だろう。自分はなぜこのような詩を書くのだろう。この宇宙の中の刹那のような時間の中で、私という存在は何なのか。そんな質問行為の繰り返しが、私にとっては詩作だ。たとえば詩は、遠い宇宙から届くかすかな光だと考えてみた。しかしそれは、唯一の答えではない。だから私はまた詩を書く」
●解説「紅梅の銀河にひびく人間の歌」(四元康佑)より
チャン・ソクの詩のなかでは、具体と抽象が、思考と感覚が、叙事と抒情が、極微と無限が、私と公が、鮮やかな劇的緊張を孕みつつ均衡を保っている。この詩集のどれひとつをとっても、彼が杜甫やウォルト・ホイットマンやヴィスワヴァ・シンボルスカに比肩する真に偉大な詩人の一員であることが証だてされるだろう。彼の詩は民族や言語や文化の壁を越えて、私たちひとりひとりの心の深みにひそむ普遍的な琴線に触れてくる。
その中核にあって、さまざまに異なる詩的要素をひとつに束ねている大本の重力のよ
うなものを「愛」と呼んだとしても、詩人は異を唱えないだろう。実際彼の詩には「詩」とともに「愛」という語がたびたび登場する。日本の現代詩にも「詩」へのメタ文学的な言及は珍しくないが、そこに「愛」が寄り添うことは極めて稀だ。私も含めて、日本の詩人にとって「愛」は使うのが躊躇われる古語、ひいては死語となりつつあるのかもしれないが、この詩集を読むと、それがどんなに異常なことなのかに気づかされる。