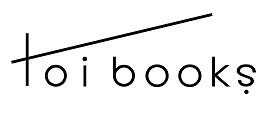『なしのたわむれ 古典と古楽をめぐる手紙』 小津夜景、須藤岳史
『なしのたわむれ 古典と古楽をめぐる手紙』
小津夜景、須藤岳史 / 素粒社 / 四六判並製 / 232P
古典と古楽は、いつだって新しい――
フランス・ニース在住の俳人と、オランダ・ハーグ在住の古楽器奏者による、言葉と音への親愛と懐疑に満ちた 24 の往復書簡。文芸と音楽、地中海と北海、断片と物語との、あざやかな響きあい。
人気ウェブ連載を書籍化。
本文より
音は振動です。振動は離れているもの同士を結びつけます。例えば二人の人が少しだけピッチの異なる同じ音を何秒か一緒に発声すると、音は自然にひとつのピッチに落ち着きます。逆に、異なるピッチのままで発声を保持するのはとても難しいことです。音は互いに引き寄せられ、溶け合うことを求めます。
対して言葉は距離を生みます。言葉は切ること、つまり意味分節の働きにその機能を負っています。そこで言葉が獲得するのはロゴスです。そしてロゴスは形式を生み出し、普遍への無限の羽ばたきを獲得します。言葉の持つ切り離す力は、思考を、そしてその人自身を辺境へと誘います。これは結びつける力、いわば抱擁とは逆に、人を心の旅へと突き動かす力です。言葉はいくつもの角を曲がり、山を越え、岬を通って海を越え、遥か遠い地平へと私たちを運びます。
(「第 4 信 辺境への誘惑」須藤岳史より)
古典に描かれた世界は、しばしば現代人からすると奇異で非日常的に感じられますが、古典とは読んで理解するよりもまず浸るものであり、溺れるものであり、追いかけても追いかけても作品に手が届かないといった距離の感覚に圧倒されるものです。作品はいつもこちらに背中を向けています。ふとした一節に「これを書いた作者はもういないんだ!」と絶句する夜も。「ひょっとしてこの作者も、さらに昔の作品の背中を追いかけていたのかしら?」と想像する朝も。いまはその背中をわたしが追いかける番らしい。わたしは駆け出す。戻らない過去へ。すると近づく。戻れない未来に。そのとき聞こえる、現在という一枚の紙が引き裂かれる音。古人とわたしがいつかめぐりあう、時のふりだしにもどる場所、それは死です。
(「第 24 信 ふりだしにもどる」小津夜景より)